総合評価:☆☆☆☆☆
感動:☆☆☆☆
ためになる:☆☆☆☆☆
面白さ:☆☆☆☆☆
読みやすさ:☆☆☆☆☆
運転者
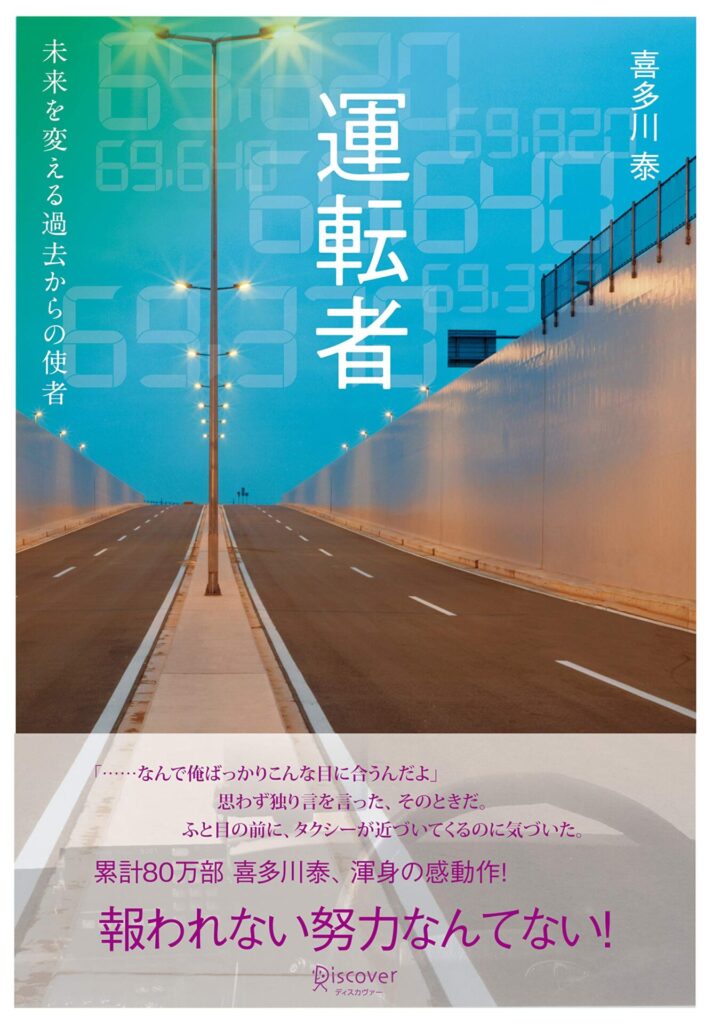
書評#20は喜多川泰(きたがわやすし)さんの小説『運転者』です。
Instagramか何かで誰かがこの本を紹介していて、それ以来気になっていたものでした。
喜多川泰さんの小説を読むのは初めてです。
とても良い小説だったので今回紹介させていただきます。
あらすじ
ネタバレにならないように簡単にあらすじを紹介します。
主人公は保険会社に勤める岡田修一、仕事でもプライベートでも家族のことでも窮地に立たされていて日々煩悶していた。
そのときに不思議なタクシーに出会う。
そのタクシーは「運を良くするタクシー」らしく、客が「運が良くなる場所」へと連れてってくれる。しかも無料だ。
無料であるには理由があるのだが、それは本編を読んでいただきたい。
そんな修一と不思議なタクシーによる心温まる物語が『運転者』だ。
人生に行き詰ってしまったとき
本の帯にはこのような感想が記されていた。
「行き詰まりを感じて苦しんでいた自分には大変心に刺さる内容でした。無我夢中で読み終え、感謝の気持ちが湧き上がりました。(30代・男性)」
「苦しいことがあっても乗り越えていける自信がつきました。どう生きていけばいいかわかり、読後は心が温かく、笑みがこぼれていました。(20代・女性)」
まさにその通りだな、と私は思いました。
私は41歳(2025年現在)ですが、人生に行き詰りを感じています。
仕事もプライベートも恋愛も、あるいは体調でさえ、うまくいかず、絶望していました。
だけどこの本を読んだことで、何かが変わりました。
絶望している状況の中、ものすごく素敵な突破口のような「希望」を見出したわけではありません。
私の生活そのものは何も変わっていません。
けれど、私が見る世界の「見方」がほんの少し変わりました。
本文の中でこんなお話がありました。
「たった一膳のごはん。それを毎日当たり前のように食べている。そんな人生を恵まれていると思えない人は、どんな人生なら恵まれていると思えるのでしょう」
引用ではなくて私なりに短くしたものです。
すごく当たり前のことを言っているのですが、この一節が深く胸に刺さりました。
よくある話といえばそうです。
「当たり前は本当は当たり前なんかじゃない。そのことに気が付き、感謝をすることが大事」
といったようなものです、言葉にしてしまえばそれまでですが、この本を読むと、その言葉の「本質」を見ることができます。
当たり前とはなんなのか。
当たり前が当たり前ではない理由は何なのか。
なぜそれを「当たり前」だと思っていたのか。
そういうことがわかります。
もう一つ心に刺さった言葉がありました。
それは、
「自分の人生が延々と続く命の物語のほんの一部である」
ということです。
人生うまくいかないと、「どうして私ばっかり」と思ったり、「なんでこんなに運が悪いんだ」と、嘆いてしまったりします。場合によっては学校や社会や他人などに責任を押し付けてしまうことだってあります。
どうしても「私」の欲望を優先してしまうのが人間です。
でも、そんな「私」とは何なのか、『運転者』という小説はそのことを教えてくれます。
そしてまた、私の「役割」というものについて。
私が生きているのは「私の欲望を満たすため」ではもちろんなく、私に与えらえた「役割」を全うする。それが「生きることだ」ということを教えてくれます。
私に子どもがいたらもっと違った捉え方もできたと思いますが、独身の私でさえ、「生きていていい」と言ってくれたような気がします。
この本は、ほんとうに人生に行き詰ってしまったときにおすすめです。
是非読んでみてください。
運とは何か
運について、私は考えました。
この小説の中では、運は「ポイントカードのようなもの」だと言っています。
運がいい、運が悪い、というものではなく、運は、「貯めて」「使うもの」だと言っています。
「徳」という考え方に似ているかもしれません。
「因果応報」という言葉でもいいのかもしれません。
「良い行いをすれば、良いことが起こり、悪い行いをすれば、悪いことがおこる」
といえるかもしれません。
そこまでは普通の考え方です。
でもこの小説の中ではもっと視点を広げています。
「運」というものは、自分一人でなんとかしたものではなく、誰かが貯めてくれた「運」を私が持っていて、それを「使わせてもらっている」という視点をこの物語は教えてくれます。
この発想はとても新しいものでした。
私が中学生のころに、社会の先生がこんなことを言いました。
「権利の上にあぐらをかいては駄目だ」と。
社会の授業の内容はほとんど覚えていないのに、この先生の言葉はそれからずっと頭の中にありました。
言葉にしてしまえば簡単なことです。
「その権利、もともとあったものじゃないよね。先人たちが苦労して手に入れたものなんだよ。それにあぐらをかいて文句や批判ばかりしていたら、バチがあたるよ」
不平や不満は、あります。
どうして自分はこんなに運が悪いんだ、と思うこともあります。
でも、日本に生まれて、それも戦争のない時代に生まれて、食べ物にも困らず、安心して寝るところもあって、そして様々な権利が保障されている。
いったいそれのどこが、「運が悪い」のだろう。
他人と比べるのは良くないことだけど、現代の日本に生まれただけでSSS級のカードを手にしているようなものである。
それでもどうして我々は不平や不満を言ってしまうのだろう。
それは「他人と比べてしまうから」だとこの本には書いてある。
「隣の芝は青く見える」とはよく言ったもので、自分が不幸だと思うとき、どうしても他人の生活をうらやんでしまう。
お金持ちの家に生まれていたら、
もっと美男美女に生まれていたら、
もっと大切にされていたら、
あの人のように、もっと友人に恵まれていたら、
と、自分と他人を比較して、「もっと」が出てしまう。
その「もっと」はきっと永遠に埋めることができないだろう。
自分と他人とではどうしても「差」が出てきてしまうからだ。
当たり前のことである。
それで、自分よりも上のクラスの人をうらやんでしまうのであるが、そこで大切なことを忘れてしまっているのだ。
「もしかしたら自分も誰かにとっては羨ましがられる存在なのかもしれない」と。
上には上がいるように、下には下がいる。
「自分よりも格下の人をみて安心しよう」というのではない。
上とか、下とか、そんなものを基準にして世界を見ていたって、そんなものは永遠に埋まらないし、まったく意味のないことだと私は言いたい。
それよりも、今の自分が存在していることに、日々感謝をすることのほうがとても大切なことだし、そしてまた、それが「しあわせ」ということなのではないだろうか。
そういうことを、この小説を読んで私は思いました。
運を貯めよう!
この小説で「運」というものの捉え方が変わりました。
私はこれまで「自分の運」ということでしか、「運」というものを見ていなかったのです。
けれど、この小説と出会ったことで、新しい「運」を見ることができました。
運とお金は似ているかもしれません。
お金があると無いでは出来ることと出来ないことがあります。
運があると無いとでも、出来ることと出来ないことが、あります。
お金があるから、お金を増やすことができる。
で、あれば、「今ある運」を増やすことも、可能ではないか。
運を増やすことは金運グッズを買うことや観葉植物を部屋に飾ることではありません。
もちろんそのことによって「気分が良くなれば」結果的に「運が良くなる」ということはあるでしょう。
小説の中で「上機嫌であれ」と何度も出てきます。
そんなこと言われても、と主人公の修一は思うし、私もそう思います。
すべてが上手くいかなくて不幸なことが続いている時に上機嫌でいることは難しいです。
でもとにかく「上機嫌でいろ」と「プラス思考」でいろと、この小説ではいっていません。
本当の上機嫌とは、本当のプラス思考とは、そのことも、教えてもらいました。
先ほど「お金」の話をしました。
映画『東のエデン』の中で滝沢朗という男の子がこういうことをいいます。
「お金を払うことよりも、お金を貰うことの方が楽しいって思える社会の方が健全的なんじゃないかって思うんだ」
運とお金が似ているのなら、こうも言えます。
「運を使うことよりも、運を貯めることの方が楽しいって思える社会の方が健全的なんじゃないか」
と。
それは社会ではなくて「自分」と言ってもいいでしょう。
自分の「運」を使うことよりも、「貯める」、運を貯めるためにはそれなりの行いをしなければならない。けれど、そのことによってたまった「運」は、自分を幸福へと導くとともに、誰かにとっての幸せとなることができる。
そういうことを思えたら、自分の人生でさえ、何かとても意味のあるものだと思えてきます。
この本を読むまで、私は絶望していました。
自分自身が嫌いで、社会も嫌いで、人生そのものも憎んでいました。
けれど、小説の読後、心のなかに何かあたたかいものが残りました。
そのあたたかいものは、すでに自分が手にしていた「運」であり、「幸福」です。
自分は全然「絶望することなんてなかったんだ」と、とても気持ちが軽くなりました。
そして、ぼんやりですが、この先の人生、どう生きたらよいのかという指針のようなものも見つけました。
運を貯める!
抽象的ですが、日々絶望してつまらなく生きているより、「運を貯めよう」と思って生きることは結果的に「希望」を見出します。
何をするでもない。上機嫌でいる。それだけで運は貯まっていきます(と本に書いてある)。
それくらいなら自分にもできそうかな、そう、思いました。
まとめ
つらつらと私の感想を述べましたが如何でしたでしょうか。
久しぶりに他人におすすめしたくなる本に出合いました。
長々と書いてしまったのでここで終わりにします。
これを読んでくださったあなたにも「運」がめぐってくるように、私は願っています。
ありがとうございました。
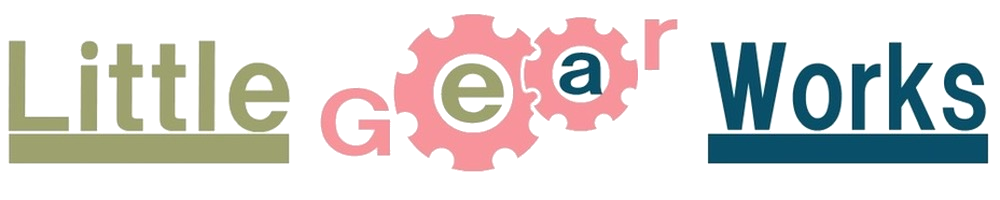
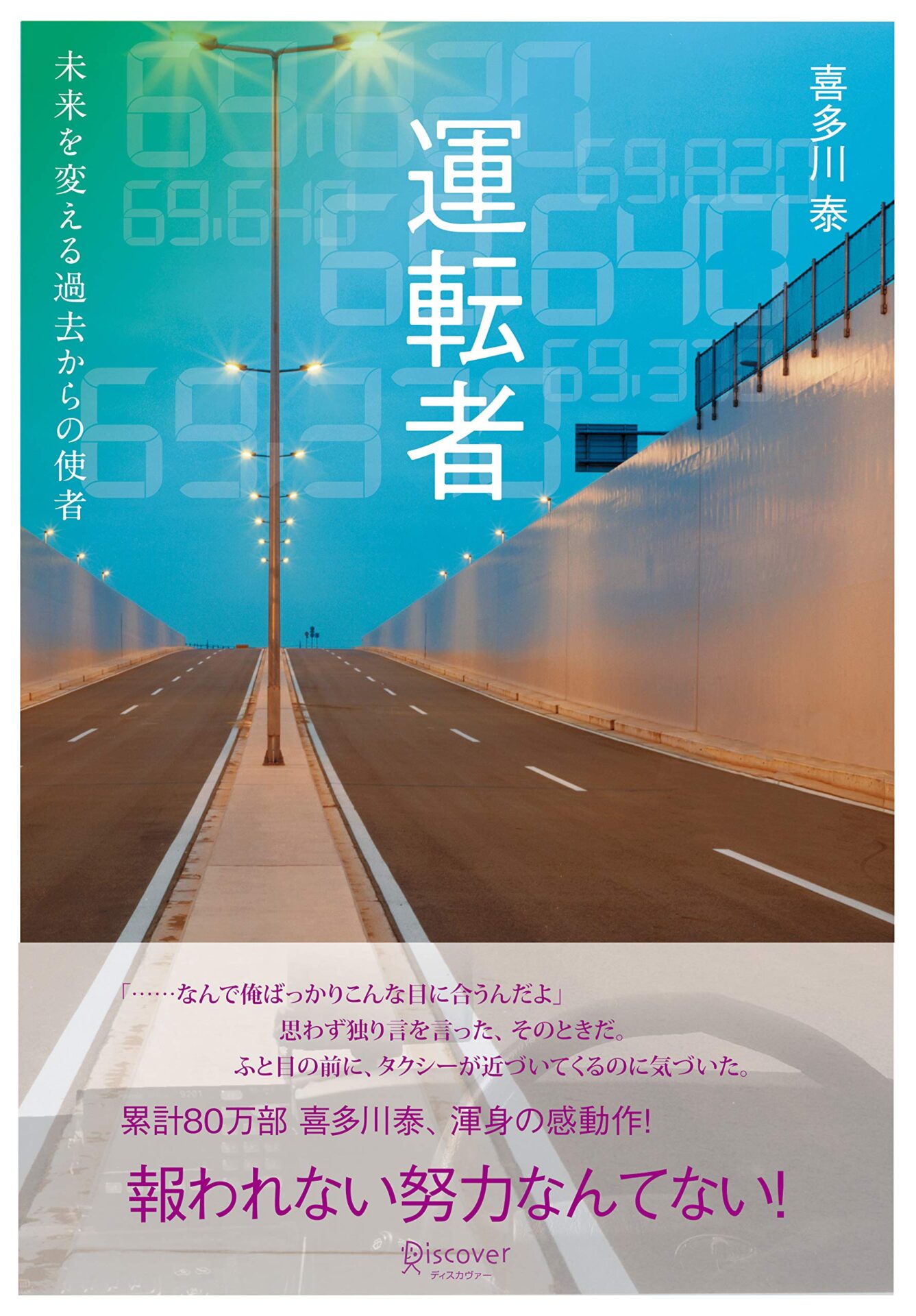

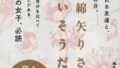
コメント