大村は僕のことが好きで、僕は大村の友だちの平岡のことが好きだった。
そして平岡は僕の兄のことが好きだった。
中学1年生のころの話である。
大村は隣の席だったので、僕によく話しかけてくれていた。
だけど僕は、平岡と話がしたかった。
別におしゃべりすることがイヤだったわけじゃない。
平岡は大村と友だちだから、大村のことを応援するだろう。
そうなると、僕の想いは届かなくなる。
平岡は平岡で僕によく話しかけてくれてはいた。
でもその内容は僕の兄に関することだった。
あまりにも兄のことを聞いてくるので、そのうち僕の名前で呼ばないで「お兄ちゃん」と呼んでくるようになった。
複雑な心境だった。
平岡と話ができることは嬉しい。
でもその内容が兄に関することだったのは癪だった。
そして僕は、兄のことが嫌いだった。
想いが繋がらないことに、やきもきしていた。
11月のころだったと思う。
僕はよく教室で寝ていた。
大村が僕を起こしに来た。
起こしにきたついでに、「誕生日に欲しいものってある?」と聞いてきた。
11月30日が僕の誕生日だったからだ。
僕はなんか送られてきてはめんどくさいなと思っていたので、「ドラえもん」だと答えた。
平岡がドラえもんが好きで、ふでばこや下敷きがドラえもんだったのを知っていたので、半分は大村に対するあてつけだった。
ドラえもんなんてプレゼントできないだろうと僕は高をくくっていた。
誕生日の当日、放課後、僕は呼び出された。
昇降口に行くと、そこには杉山が立っていた。
杉山は紙袋を持っていて、僕に渡してきた。
「大村から」
なぜ大村が直接渡しに来なかったのか不思議だったが、とりあえずその紙袋を受け取った。
紙袋の中には、ドラえもんのぬいぐるみが入っていた。
冬が過ぎ、春が来て、クラス替えが行なわれた。
いつのまにか、それぞれの恋はどこかに消え去っていた。
僕はそのころ、不思議な感情を持っていた。
ただの友だちだったらいいのだけど、その友だちが自分に好意を抱いてくると、嫌悪感を抱くようになっていた。
うざい、気持ち悪い、と、思っていた。
なので、中学1年の僕は大村の気持ちから逃げていたのだ。
その気持ちの尊さを知るのは、それからずっとあとのことである。
高校の3年生になっていた。
中学を卒業し、それぞれがそれぞれの道に進んでいた。
高校生になったら彼女を作るぞと意気込んでいたものの、誰ひとりとして僕と付き合ってくれる子はいなかった。
そもそものところ、ほとんど男子校だったので、出会いそのものもなかった。
ふいに僕は大村のことを思い出した。
大村は、僕のことが好きだったのだ。
元は、大村のことをいい奴だと思っていたのに、大村が好意を持ってくれたことで、僕は大村のことを邪険に扱うようになった。
そして、逃げた。
大村はあのとき、どんな想いだったのだろう。
そんなことを考えた。
どんな気持ちで、あのドラえもんのぬいぐるみを買ったのだろう。
どんな気持ちで、プレゼントを僕に渡そうとしてくれていたのだろう。
僕がその気持ちを踏みにじったことで、大村はどう感じたのだろうか。
きっと傷ついた。
きっと傷ついた。
きっと、傷ついた。
僕は物を大切にする性分で、しっかりとそのぬいぐるみは部屋に飾ってあった。
そのドラえもんを見ながら、「謝りたい」と強く思った。
夏休みだっただろうか。
僕は大村の家に電話をかけてみた。
親が出たらどうしようと心臓がバクバクしていたけれど、ありがたいことに大村本人が電話に出た。
僕のことを覚えてる? と聞くと、覚えてるよと返ってきた。
「会いたい」と僕は言った。
ため息が電話口から聞こえたような気がする。
それでもなんとか会う約束は取れた。
小学校の校門を待ち合わせ場所にした。
僕はリュックにドラえもんのぬいぐるみを入れて、小学校へ向かった。
約束の時間よりも早く着いたせいか、そこには誰もいなかった。
大村がちゃんと来てくれるか心配だった。
待っている時間がとても長く感じた。
しばらくして、大村がやってきた。
僕はとても緊張していた。
「座って」と僕は言った。
石の、何かの縁(ふち)に大村が座り、その横に僕は座った。
僕はリュックからドラえもんのぬいぐるみを取り出した。
「覚えてる?」
大村がどう答えたのか覚えていない。
僕は自分の気持ちを正直に告白した。
プレゼントを貰って迷惑に思っていたこと、大村の気持ちを知っておきながら何も言わずに関係を絶ったこと、そして最近になって、そのことがとても申し訳ないと思うようになったこと。
「ごめんね」と僕は何度も謝った。
大村の表情は読み取れなかったけれど、ひとつだけ分かったことがあった。
いまの大村は僕のことを好きではない
ということだった。
たぶん僕がしたことは、ただの自己満足だったのだと思う。
もしかしたらいちいち過去のことを掘り返したりしないで、そっとしておくべきだったのかもしれない。
でも僕は、謝らないわけにはいかなかったし、少しのあいだだったけれど、僕のことを好きでいてくれたことに感謝をしたかった。
僕の告白を受けて、大村がどう思ったのか分からない。
泣きもしなかったし、困ったようでもなかったし、怒りもしなかったし、笑顔もなかった。
まるでもう、僕と大村は「他人」だと言わんばかりだった。
思い出話も、近況報告もなかった。
「これからもよろしく」なんて言葉さえ交わされなかった。
どのように「バイバイ」したのか覚えていない。
「元気でね」くらいは言ったのかもしれない。
でも、その後大村と会うことは二度となかった。
ーーーーーーーーーーーー
あれから20年以上が過ぎたいま、中学時代の友だちとはまったく会ってはいない。
連絡先さえ知らない。
同窓会すら開かれない。(あるいは自分が誘われないだけか)。
成人式の日に、一度だけ会ったが、それだけだった。
旧友と再開して、写真を撮ったり、一緒に煙草を吸ったりしてみたけれど、もう僕たちは友だちには戻れなかった。
二次会もなかった(誘われなかっただけかもしれないが)。
「私のことを忘れないでね」と言ったのは小説『ノルウェイの森』に出てきた直子だったろうか。
みんなは、僕のことを忘れてしまったのだろうか。
大村は、僕のことを忘れてしまったのだろうか。
あのころたしかにあった「想い」はいったいどこへ消え去ってしまったのだろう。
ときどき僕は、夢の中で旧友たちと出会う。
たぶんきっと、現実では二度と会うことはないだろう。
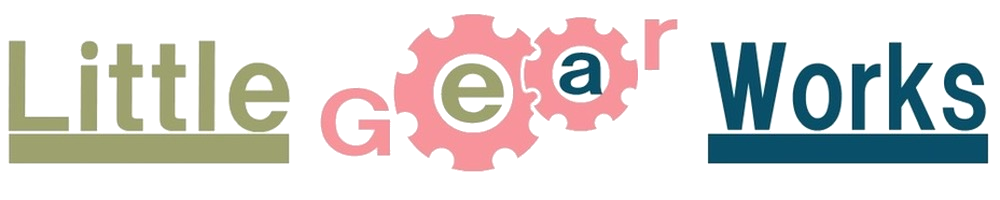



コメント